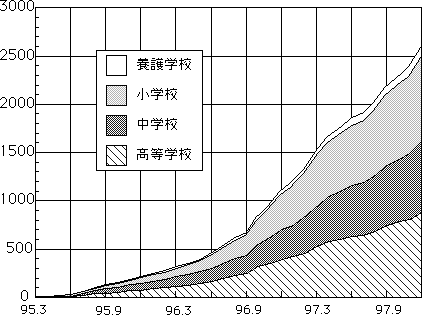
|
|
1.はじめに 2.学校のホームページの現状 3.インターネットと教育・学習情報資源 4.インターネットと交流・共同学習 5.まとめ |
〒582-8582 大阪府 柏原市 旭ケ丘 4-698-1 大阪教育大学 理科教育講座(物理) 越桐 國雄 TEL:0729-78-3373 ( 共通FAX:0729-78-3366 ) koshi@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 1998年6月22日公開、6月27日訂正 |
昨年に引き続き,日本国内におけるインターネットの教育利用の動向を,学校ホームページの開設状況の分析および学校のホームページ管理者に対して実施した調査によって検討する.このために,1995年3月から3年間にわたって実験的に運用してきた教育情報リンク集「インターネットと教育」のページで定期的に収集しているURL情報,および1998年の1月に実施した全国の学校のホームページ管理者に対するアンケート調査結果を用いた.
公開されている国内の小学校,中学校,高等学校,盲・聾・養護学校のホームページの合計の総学校数に対する比率は,昨年同期の3%から7%にまで増加している. 調査対象となった学校の86%はインターネットに接続していたが,インターネットに接続できる端末数が3台以下の学校が58%あり,教職員の使えるメールアカウントが3以下の学校が72%に達しているなど,設備や環境の整備の観点からはまだかなり問題が多いことも判明した.
キーワード: インターネット,学校,教育・学習情報,ホームページ,電子メール日本国内のインターネット教育利用プロジェクトの先駆けとなった100校プロジェクト(ネットワーク利用環境提供事業)[1]の活動が開始されてからほぼ3年を経過し,インターネットの教育利用は着実に展開を続けている.文部省は,第15期の中央教育審議会の1次答申[2]を受けて,2003年までに国内のすべての小・中・高等学校などをインターネットに接続することを表明している.この決定は地方自治体にも通達され,今後毎年4000〜8000校の単位で学校が順次インターネットに接続されることが予想できる.また,インターネットの教育利用はこれまでの全国的なプロジェクトに加えて,各地方自治体における教育情報ネットワークへと広がっており,地域間,学校間の格差をはらみながらも,教育情報環境の著しい変貌をもたらしつつある.
このように急速に変化しつつある日本国内のインターネットの教育利用の現状を把握し,問題点を抽出するために,インターネットにおける学校ホームページの開設状況の調査と学校のホームページ管理者を対象としたアンケートを行った.このような調査としては,我々の前々回,前回の調査[3,4]以外にも,100校プロジェクト参加校を対象として1995年度に山内が実施したもの[5],1996年度の文部省委託事業として,日本教育工学振興会の情報通信ネットワークの教育利用に関する調査研究運営委員会が実施したもの[6]がある.
後者は,こねっと・プラン参加校や100校プロジェクト参加校を中心とした1600校に対する広範な調査であり,運用の実態にまで踏み込んだ精緻な調査になっている.一方我々は,これに比べて調査項目は少ないが,対象を特定のプロジェクト校中心に絞るのではなく,インターネットの教育利用の全体的状況を把握することを目標として,全国のホームページを公開している学校を対象としたこと,また回答者として,実際にインターネット教育利用の最前線で活躍している学校のホームページ管理者の先生方を対象としたこと,などが特徴となっている.前回までの調査では,リソース(教育・学習情報資源)に重点を置いていたが,今回はこれに加えて,コミュニケーション・コラボレーション(交流・共同学習)に関する項目も含めた.
電子メールによるアンケート「インターネットの教育利用の現状に関する調査」は1998年1月11日〜1月31日に実施された.今年度は,1997年12月27日版の「インターネットと教育」[7]に記載されている2783校(高 1015,中 783,小 876,特 109)の学校のページの管理者(原則として各校1名)を対象とした.このうち電子メールアドレスが記載されていたものが,2211校(高 842,中 589,小 703,特 77)で,電子メールアドレスの記載率は79%であり,昨年の記載率75%より若干増加している.
これにもとづいて各都道府県別に調査依頼メールを発送し,710校(高 266,中 187,小 221,特 36)の有効回答を得た.回答率は32%であり昨年の回答率52%に比べて少なくなっている.この原因はいくつか考えられるが,電子メールの利用によってこの種の調査が容易に行えるようになり,類似内容の調査がこれらの学校に集中して行われていることが回答者からも指摘されている.学校に対してインターネットを利用した調査を行う場合はなるべくその結果を広く公表し,不用な重複調査による学校への負担を軽減するための方策を検討する必要があるだろう.
前回も我々が指摘したように[4],教育委員会で承認された公式なものから,個人による実験的な性格のものまで幅広く存在する学校のホームページを定義することは,現段階では必ずしも容易ではない.そこで我々は,一般的なディレクトリサービス(リンク集)で収集されている「学校のページ」の実態に近いものとして,以下の基準を当てはめている.
我々が実験的に運用している教育情報リンク集「インターネットと教育」では,更新されたリンク情報を週単位で蓄積しているため,学校ページ数の時間的変化を調べることが可能となっている.但し昨年度と比較すると,地方自治体による教育情報ネットワークの整備が全国各地で進んでいるため,学校ホームページの増加数も著しくなっており,学校ホームページの補足率は80〜90%程度と推定される.昨年までのような指数関数的な増加ではなく,図1のように28校/週程度の割合で時間にほぼ比例して増加している.なお,昨年および一昨年の平均増加率は,それぞれ,23校/週,6校/週程度であった.
今回のアンケート調査に用いた1997年12月27日版の「インターネットと教育」の学校ページのデータによれば,現在,全国の高等学校の18.5%(8.4%),中学校の7.0%(3.1%),小学校の3.6%(1.6%),盲・聾・養護学校の11.1%(4.8%),合わせると日本の学校の6.6%(3.0%)がインターネット上にホームページを公開しており,この1年でほぼ倍増していることがわかる(カッコ内は昨年同期の値).
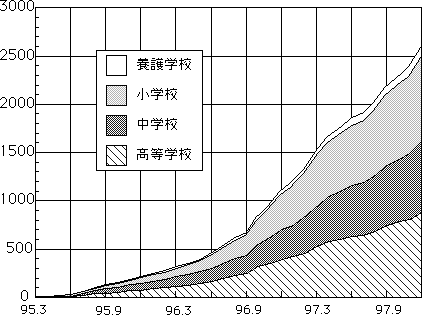
|
図1 学校ホームページの開設数の推移
さて,1997年12月27日版の「インターネットと教育」の学校ページのデータから,都道府県別のホームページ開設数を求め,これをその都道府県の総学校数(小学校+中学校+高等学校+盲・聾・養護学校)で割ったものを,学校のホームページの都道府県別開設比と呼び,図2に表した.学校数は平成9年度の文部省の学校基本統計調査報告による.
上位12県をあげると,岐阜県(15.0%),佐賀県(13.9%),石川県(11.8%),山梨県(11.7%),富山県(11.7%),福井県(11.4%),秋田県(11.1%),長野県(10.7%),高知県(10.5%),香川県(9.9%),京都府(9.8%),新潟県(9.5%)となる.なおこれらの府県の多くでは,地方自治体による教育情報ネットワークの整備が進行中である.開設比が下位の県では3%程度であり,上位県とかなりの差が存在している.ただし,接続されてはいてもインターネット上では非公開となっている学校の数はここには反映されていない.また,この開設比は実際の活動の質までとらえるものではなく,都道府県別開設比にかかわらず,非常に先進的で活発な活動を行っている学校は全国に存在している.
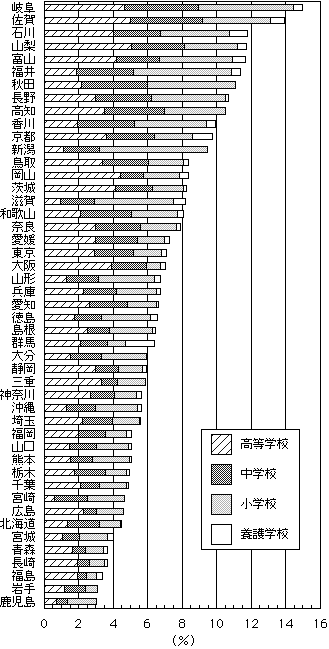
|
図2 学校ホームページの都道府県別開設比
先に述べたように,ここでは学校のホームページとして,公式ページだけではなく非公式な実験的ページまで含めている.しかしながら,非公式なページの割合はそれほど大きくなく,前回の33%から,今回は24%へと減少している.また,私立の高等学校などを中心とした学校案内・入試情報提供のページの増加がやや目立ったが,過半数は学校の教育・研究活動の一環として運営されていることがわかる.
なお,回答者のうちで,新100校プロジェクト参加校は32校(73校),こねっと・プラン参加校は123校(430校)であり(カッコ内は調査依頼メール発信数),これら公式ページを持ったプロジェクト参加校の回答回収率は,全体平均の32%と大差ない31%であった.
表1 学校のホームページの運用形態
| 運用形態 | 1998.1 | 1997.1 | |
| 1 | 学校公認,学校案内,入試情報などの提供 | 22 % | 15 % |
| 2 | 学校公認,学校の教育・研究活動の一環 | 51 % | 49 % |
| 3 | 教師個人(クラス等)の活動,学校として了解 | 19 % | 24 % |
| 4 | 教師個人(クラス等)の活動,学校として未認知 | 3 % | 6 % |
| 5 | PTA,児童・生徒,学校関係者の活動 | 2 % | 3 % |
| 6 | その他・無回答 | 3 % | 4 % |
昨年6月の文部省の調査によれば,全国の公立学校の9.8%がインターネットに接続されており,また我々のデータから,その時点で全国の学校の4.6%が学校のページを持っていた.つまりインターネットに接続されている学校のほぼ半数近くがホームページを公開していることになる.また,表2からわかるように,ホームページを公開している学校の86%がインターネットに接続されている.
昨年からの推移で特徴的なことは,ISDNのダイヤルアップ接続が48%と主流を占めるようになったことである.これは,都道府県の教育センターなどによる教育情報ネットワークの整備がISDNのダイヤルアップ接続を中心として進んでいることと連動している.専用回線については新100校プロジェクトの設備高度化によってアナログ専用線が減っていることがやや目立つ.なお,LAN直結には,CATV回線を利用したインターネット接続などの形態も含まれている.
表2 学校のインターネット接続形態
| 接続形態 | 1998.1 | 1997.1 | |
| 1 | 学校はインターネットに接続されていない | 12 % | 25 % |
| 2 | 公衆回線(ダイヤルアップ、アナログ) | 18 % | 28 % |
| 3 | 公衆回線(ダイヤルアップ、ISDN) | 48 % | 23 % |
| 4 | 専用回線(アナログ3.4kHz) | 2 % | 6 % |
| 5 | 専用回線(デジタル64kbps〜,OCNエコノミ等) | 14 % | 12 % |
| 6 | LAN(イーサネットなど)に直結 | 4 % | 4 % |
| 7 | その他・無回答 | 2 % | 2 % |
さて,学校のインターネットへの接続は早い勢いで進んでいるが,現場の学校の教師からは多くの問題点が指摘されている.前回は設備(ハード)と運用(ソフト)の問題を十分区別できなかったので,今回,設備に関した問題を別の項目として質問した.この結果,もっとも多かったのは,「校内ネットワークの整備が不十分である」という回答であり,47%に達した.また,「インターネットに接続できるコンピュータの数が少ない」が42%でこれに続く.
これに対して,回線容量や費用の問題はそれほど重要視していない学校が多かった.さらに,学校の中のインターネットに接続されたコンピュータの台数も尋ねたが, 0台(5.1%),1台(31.7%),〜 3台(20.7%)などとなっており,6割近くは端末数が3台以下であり,特にコンピュータの導入の遅れている小学校でこの傾向が強い.
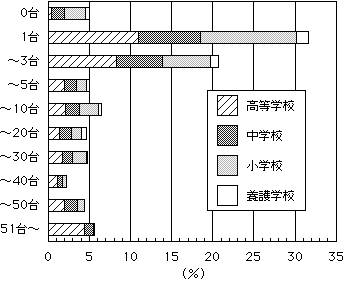
|
図3 接続された端末数
インターネットの教育利用を進めるためには,まず回線の設置が必要であるが,これと並行して,校内ネットワークの整備やインターネットに接続されるコンピュータの台数の確保が欠かせないことがわかる.
表3 設備上の問題点 (2項目選択,計200%で表示)
| 設備上の問題点 | 1998.1 | |
| 1 | 校内ネットワークが未整備で利用できる場所が限定 | 47 % |
| 2 | インターネットに接続できるコンピュータの数が少ない | 42 % |
| 3 | 保守運営費用が不足,システムの維持が十分できない | 18 % |
| 4 | 回線接続費用が不足し,回線容量(アクセス速度)が不十分 | 14 % |
| 5 | 回線接続費用が不足し,接続時間が十分に確保できない | 12 % |
| 6 | メールアカウントの発行が自由にできない | 12 % |
| 7 | インターネットに接続できるコンピュータの機能が不十分 | 10 % |
| 8 | WWWサーバが校内になく,ホームページの更新が容易でない | 6 % |
| 9 | その他・無回答 | 39 % |
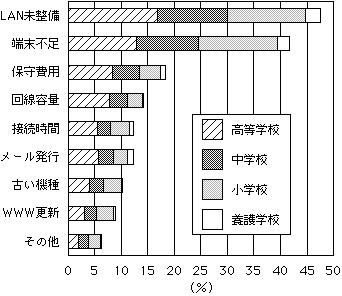
|
図4 設備上の問題点