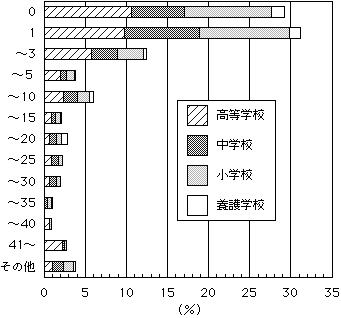
|
図5 教職員のメールアカウント
|
1.はじめに 2.学校のホームページの現状 3.インターネットと教育・学習情報資源 4.インターネットと交流・共同学習 5.まとめ |
〒582-8582 大阪府 柏原市 旭ケ丘 4-698-1 大阪教育大学 理科教育講座(物理) 越桐 國雄 TEL:0729-78-3373 ( 共通FAX:0729-78-3366 ) koshi@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 1998年6月22日公開、6月27日訂正 |
インターネットの教育利用は,リソース(教育・学習情報資源)の利用や提供と,コミュニケーション・コラボレーション(交流・共同学習)に大きくわけられるが,まずこのために必要な情報の入手経路を質問した.結果は表4に示されており,昨年とほとんど同じ結果となったが,WWWの利用がネットサーフィンから検索エンジンを用いた目的意識をもった探索に移行している様子がわかる.電子メールやネットニュースなどの使われ方もほとんど昨年と変わっていない.
また,日本国内の教育,学習に関する情報を探す際にどのページを見るかをあわせて質問しているが,YAHOO! JAPANが72%と圧倒的に多く,「こねっと・プラン」の25%と「インターネットと教育」の25%がこれに続いている.他の教育情報に特化した情報リンク集の利用度はそれほど高くない.一方,全文検索型のサーチエンジンgooは12%であり,前項目の情報の入手経路で,WWW(検索エンジン)とWWW(リンク集)が2:1の比であったことと合わせて考えれば,ディレクトリサービスのYahooでキーワード検索しているユーザが多いということになろう.
表4 インターネットの教育情報の入手経路 (2項目選択,計200%で表示)
| 教育情報の入手経路 | 1998.1 | 1997.1 | |
| 1 | WWW(検索エンジン:キーワードによる検索) | 53 % | 46 % |
| 2 | 書籍,雑誌,新聞など既存のメディア | 49 % | 53 % |
| 3 | 電子メール,メーリングリスト | 36 % | 36 % |
| 4 | WWW(リンク集:カテゴリー別索引による探索) | 27 % | 23 % |
| 5 | WWW(ネットサーフィン) | 19 % | 23 % |
| 6 | 同僚,友人,知人などとの直接の会話 | 11 % | 12 % |
| 7 | ネットニュース,BBS・会議室・フォーラム | 5 % | 5 % |
| 8 | その他・無回答 | 0 % | 1 % |
さらに,現在インターネット上で不足している教育・学習情報を質問した.結果は表5に示されており,教育実践事例報告が45%で昨年と同様に1位で,学習指導案・授業案が28%でこれに続く結果となった.このような具体的な授業に直接役立つ情報の次に,教育用ソフトウェア,電子図鑑,電子教科書,電子年鑑のような教材,素材データが位置し,その後,国内外の交流先や共同学習の案内などの交流・共同学習に関する情報となっている.現場の教師のニーズが教育実践事例報告や学習指導案・授業案にあるということは,逆に教師自身が情報発信を要求されているということにほかならない.
表5 不足している教育・学習情報 (2項目選択,計200%で表示)
| 不足している教育・学習情報 | 1998.1 | 1997.1 | |
| 1 | 教育実践事例報告 | 43 % | 35 % |
| 2 | 学習指導案・授業案 | 28 % | 14 % |
| 3 | 教育用ソフトウェア | 22 % | 20 % |
| 4 | 電子図鑑・画像資料(素材) | 22 % | 21 % |
| 5 | 電子教科書・参考書 | 14 % | 17 % |
| 6 | 電子年鑑・統計資料(素材) | 14 % | 10 % |
| 7 | 国内交流先紹介 | 11 % | 19 % |
| 8 | 国際交流先紹介 | 11 % | 16 % |
| 9 | 共同学習企画案内 | 10 % | 7 % |
| 10 | 催し物・研究発表会 | 8 % | 9 % |
| 11 | 図書館・文献情報 | 8 % | 8 % |
| 12 | 美術館・博物館情報 | 3 % | 6 % |
| 13 | その他・無回答 | 6 % | 11 % |
さて,これらの情報受信時および発信時における問題点をそれぞれ2項目選択してもらった結果が表6および表7である.受信時の問題点の1位から3位までが,学習・教育の場で利用可能な情報の絶対量が少ないことやこれを探し出すことが容易でないことを示している.一方,4位から7位までは情報の質の問題であり,マスコミ等で話題になる児童生徒に有害な情報を遮断できないという問題は5位にとどまっている.これは学校内にまだ十分な環境がなく,児童生徒が自由に検索システムを利用するような実践が少ないためではないかと考えられる.また,情報発信に関しては,校内組織の未整備が58%で,これにコンテンツ作成や情報更新の手間が続いている.
表6 情報受信時の問題点 (2項目選択,計200%で表示)
| 情報受信時の問題点 | 1998.1 | |
| 1 | 過剰な不用情報の中に必要な情報が埋没 | 57 % |
| 2 | 情報が一般向けで,教育用ではない | 46 % |
| 3 | 必要な情報が存在しない | 25 % |
| 4 | 著作権の問題で情報を再利用できない | 18 % |
| 5 | 児童生徒に有害な情報を遮断できない | 18 % |
| 6 | 情報の信頼性に不安がある | 15 % |
| 7 | 情報が外国語のままである | 9 % |
| 8 | 情報が頻繁に移動,変更されている | 3 % |
| 9 | その他・無回答 | 9 % |
表7 情報発信時の問題点 (2項目選択,計200%で表示)
| 情報発信時の問題点 | 1998.1 | |
| 1 | 校内の組織が未整備である | 58 % |
| 2 | コンテンツの作成に手間がかかる | 34 % |
| 3 | 情報の更新作業に手間がかかる | 33 % |
| 4 | 個人情報保護条例による制約が大きい | 20 % |
| 5 | 教育効果がうまく評価できない | 19 % |
| 6 | 発信内容の承認手続きが面倒 | 12 % |
| 7 | WWWページへの返事,応答が少ない | 8 % |
| 8 | WWWページへのアクセスが少ない | 4 % |
| 9 | その他・無回答 | 12 % |
インターネットにおける,交流・共同学習をすすめるにあたっての最低限の条件として,教師あるいは児童生徒が電子メールを使えることがあげられるだろう.そこで,ここでは交流・共同学習の現状や問題点とともにコミュニケーション環境の整備状況の基礎データとなる電子メールアカウントの発行数を調べた.まず,これまで,交流・共同学習を行ったことがあるかどうかを質問した.この結果が表8に示されている.経験なしが41%を占めているが,国内(県外)との交流が30%,海外との交流も18%に達していることがわかる.これに比べて,地域(同一自治体)あるいは校内など,身近な範囲での実践はそれほど多くない.
表8 交流・共同学習の経験 (2項目選択,計200%で表示)
| 交流・共同学習の経験 | 1998.1 | |
| 1 | なし | 41 % |
| 2 | 国内(県外)のクラス・学校と | 30 % |
| 3 | 海外のクラス・学校と | 18 % |
| 4 | 国内の学校外の人々と | 16 % |
| 5 | 地域(同じ自治体)のクラス・学校と | 13 % |
| 6 | 地域の学校外の人々(PTA,社会人,学生など)と | 13 % |
| 7 | 校内のクラス,学年間で | 8 % |
| 8 | 海外の学校外の人々と | 7 % |
| 9 | その他・無回答 | 54 % |
表9 交流・共同学習の問題点 (2項目選択,計200%で表示)
| 交流・共同学習の問題点 | 1998.1 | |
| 1 | メールアカウントが不足している | 46 % |
| 2 | 国内交流・共同学習の相手が見つからない | 26 % |
| 3 | 児童・生徒のプライバシーが保てるか不安 | 23 % |
| 4 | 教育効果がうまく評価できない | 21 % |
| 5 | 意思疎通がうまくできず,交流が長続きしない | 18 % |
| 6 | 言葉や習慣の壁 | 13 % |
| 7 | 国際交流・共同学習の相手が見つからない | 11 % |
| 8 | いやがらせメール,広告メールなどが防げない | 5 % |
| 9 | その他・無回答 | 37 % |
また,電子メールのアカウントの発行数では,教職員と児童生徒に対するものをそれぞれ図5と図6に示した.教職員に関しては,29%の学校でグループアカウントも含めて電子メールアカウントが発行されていない.また,学校で1アカウントというところも31%であり,アカウント数が3以下の学校が72%に達している.
児童生徒に関しては74%の学校でメールアカウントが発行されておらず,交流・共同学習を進める際の大きな障害となる可能性がある.実際,表9に示したように,交流・共同学習を進めていく上での問題点を質問したところ,46%がメールアカウントの不足をあげている.次に相手が見つからない26%,プライバシーが保てるか不安23%などとなっていた.
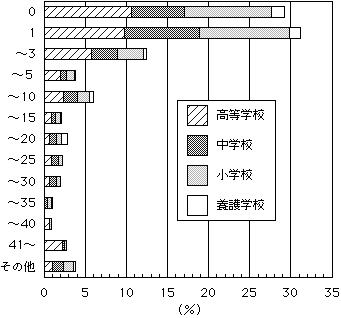
|
図5 教職員のメールアカウント
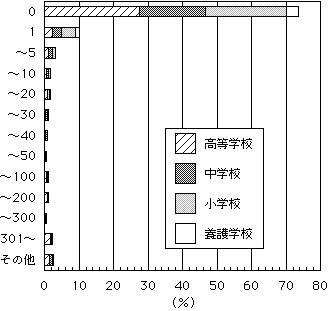
|
図6 児童生徒のメールアカウント
国内におけるインターネットの教育利用の現状を,我々が実験的に運営している,教育情報リンク集「インターネットと教育」および学校のホームページ管理者へのアンケート調査から分析した.インターネット上にホームページを持つ学校の数は全国の7%に達し,毎週30校近くの割合で増加している.今後のインターネットの整備計画から判断して,この数字はここ数年の間は40〜80校/週程度で推移することが予想される.このような急成長の一方で,学校内のインターネット接続可能端末や校内ネットワークの整備が進んでいないことも明らかとなり,校外ネットワークと校内ネットワークのバランスのとれた整備が今後必要になってくるであろう.
現時点において,学校のインターネットへの接続は,地方自治体の教育センターなどをハブとするISDNのダイヤルアップ接続が中心で,これが接続形態のほぼ半数近くを占めている.しかしならがらこの方法では回線費用などの制約などにより,各クラスからいつでも自由に利用するような形態があまり容易でないことも予想され,引き続き専用線による接続の可能性を追求すべきであろう.
また,都道府県や政令指定都市など大規模な自治体の教育センターによるサーバ集中管理方式では,各学校のメールアカウントの発行などに大きな制約が生じることも考えられ,今後各学校あるいは学校群単位(例えば中学校区の小学校と中学校のユニット)などでサーバを設置するための技術的あるいは人的,予算的な課題を解決してゆく必要があろう.実際,今回の調査では,各学校の先生が個人のメールアカウントを学校に持つという状況にはまだ遠いことが明らかとなっている.
インターネットの教育利用のための基盤整備における第一段階の目標は,全国の学校をインターネットに接続することであるならば,次の段階ではすべての教師がメールアカウントをもって自由に交流できる環境の整備に目標を置くべきであるかもしれない.このような環境を日常的に経験することによってはじめて,授業の中でのインターネットの活用の展望が開けてくるのではないだろうか.
この調査は,日本教材文化研究財団の「教育におけるマルチメディア・インターネットの効果に関する研究(座長:坂元昂先生)」から一部援助を受けています.
WWWのフォームとして提示した調査票はここを参照されたい.回答されたフォームは,集計者にメールで転送されるよう設定した.また,直接メールによる回答希望者には,同内容の調査票をメールで送信している.なお,発送した2211通のうち,91通(4.1%)は相手先アドレスが見つからずリターンメールとなった.調査依頼メールは1月11日に発送し,509件の回答が確認された1月23日に再送し,最終的に710件が有効回答となった(最終的に2月7日到着分までを集計した).なお,メールによる回答があったのはそのうち19件(2.7%)であった.
なお,回答者の内訳は以下のとおりである.